OECD日本政府代表部職員の声:村尾崇参事官
OECDと日本の教育政策
OECD日本政府代表部参事官 村尾崇

私は、2013年春に文部科学省からOECD日本政府代表部に出向し、OECDの活動のうち教育分野に関する日本政府・OECD間の調整を担当しています。OECDと日本の教育政策の関わりについて、OECD日本政府代表部の役割も含めながら、ご紹介したいと思います。
1 OECD日本政府代表部の役割
OECD(経済協力開発機構)は、その名称から、経済分野の国際機関というイメージが持たれがちですが、実際には経済や開発だけでなく、教育や医療、雇用など社会政策も含め、幅広い分野をカバーしています。
OECD加盟国は24カ国の時代が長く続き、OECDは「先進国クラブ」と揶揄されることもあったようです。しかし、世界経済における新興国の影響力が20年前に比しても格段に増し、先進国の経済的比重が低下している中、現在の加盟国は34カ国に増加しており、新規加盟審査中の国や、加盟国ではないが「キー・パートナー」として特別に位置づけられている新興国(ブラジル、インド、インドネシア、中国、南アフリカ)もあります。我が国の置かれている状況や他国からの我が国に対する見方も刻々と変化しています。
教育に限りませんが、OECDの強みである客観的なデータや分析を国内に伝えるだけでなく、我が国の立場を正確に海外に発信し、理解を得るためには、正確な情報を収集してこうした状況の変化を見極めることや、国内事情を必要に応じて説明することが大切です。このため、OECD本部所在のフランス・パリに常駐する日本政府代表部において、常日頃からOECD事務局や他国代表部と信頼関係を構築することが重要になってきます。
2 OECDと教育
教育分野においては、例えば、15歳時点の読解力、数学的リテラシー及び科学的リテラシー等の学習到達度を3年ごとに測定しているPISA(生徒の学習到達度調査)は、OECD加盟国以外にも多くの参加国を集めている国際調査プロジェクトであり、我が国を含む各国の教育政策の方向性に大きな影響を与えています。2015年には、新たに「協同問題解決能力」も調査されるなど、時代の要請に応じてPISAも変化しています(結果の公表は2016年12月予定)。
OECDではこの他にも、成人に必要なスキルを測定するPIAAC(国際成人力調査)、学校の教員に関して総合的に調査するTALIS(国際教員指導環境調査)等の大型の国際調査を実施しているほか、ECEC(幼児教育・保育)、VET(職業教育訓練)、教育行政のガバナンスの在り方、子供の社会情動的スキルの発達など、多様なテーマにおいて国際的なデータ収集・分析や研究を行い、各国の教育政策立案に資することを目的とするプロジェクトが展開されているところです。(なお、OECDの教育関係プロジェクトの概要をお知りになりたい方は、下記サイトの「Ⅸ.教育」の項をご覧下さい。)
http://www.oecd.emb-japan.go.jp/about/index.html#about9
教育については、個人的な体験などを基に語られがちな面もありますが、客観的な統計・データやその分析を踏まえた「エビデンス・ベースト」(evidence based)な教育政策を立案するため、また、我が国の教育を国外に発信するためにはOECDの強い対外発信力が有効であるという観点からも、我が国にとってOECDを活用することはますます重要になってきています。こうした観点からなされた調整の一例としては、2016年5月14-15日に岡山・倉敷において開催されるG7教育大臣会合へのOECDの参加があります。同年5月26-27日には日本が議長国を務めるG7サミット(主要国首脳会議)が伊勢・志摩において開催されますが、G7教育大臣会合はこれと合わせて開催されるものであり、このような場で政策議論を深める上で有益と考えられることから、同教育大臣会合にもOECDが参画することとなったものです。
3 「OECD東北スクール」プロジェクト
東日本大震災発生直後の2011年4月、訪日したグリアOECD事務総長が震災復興に協力することを約束したことを契機として、2012年3月、福島大学、日本政府、OECDが連携した復興教育プロジェクト「OECD東北スクール」が誕生しました。具体的内容は、震災被災地の岩手、宮城、福島の中高生約100名が集まり、「2014年夏に、パリで東北の魅力を世界にアピールするイベントを実施する」という目標の下、国際的なイベントの企画・立案・実施を資金調達も含めて生徒が中心になって行うというプロジェクト学習です。イベント実施はあくまでも「手段」であり、生徒たちがプロジェクトに取り組む過程を通じて、リーダーシップや実践力、国際性、問題解決能力等を培うことが「目的」です。
生徒たちだけでなく、大人を含めて誰もが手探りのプロジェクトだったわけですが、①最終的なイベント実施が国内ではなく仏・パリであること、②OECDとの間で種々の調整が必要であったこと、から、OECDで開催される各種会議対応等の通常業務に加えて、私も本プロジェクトに大きく関与することになりました。
幾多の困難を乗り越えて、2014年8月30-31日には、パリのエッフェル塔の下に広がるシャン・ド・マルス公園において生徒たちが企画したイベント「東北復幸祭」が実施され、多くの来場者を集めました。また、9月2日にはOECD本部において、プロジェクトの象徴として「桜の植樹」が実施されるとともに、生徒たちが海外の生徒や、同行した大人も交えて「2030年の学校」像を議論する「生徒大人合同熟議」も行われました。これらの過程を通して、参加した生徒たちは、例えば、実際に海外からの視点に直接接したことによって、物事を相対的に考えることの重要性を実感するなど、多くのことを学ぶことができました。
(なお、「OECD東北スクール」について更に詳しくお知りになりたい方は、下記サイトをご覧ください。)
http://www.oecd.emb-japan.go.jp/tohoku/index.html
これら一連の行事そのものは成功したと考えて良いと思いますが、これを一過性の「イベント」に終わらせず、将来の教育の在り方の議論につなげてこそ、我が国にとっても、OECDにとっても、意義あるプロジェクトであったといえることになります。

東北復幸祭(2014年8月30-31日)©OECD/Marco Illuminati

OECD本部における植樹(2014年9月2日) ©OECD/Hervé Cortinant
4 今後の教育の方向性
「OECD東北スクール」プロジェクトを一つの契機として、OECDでは、変化の激しい時代の中で「2030年に向けて育成していかなければいけないスキルは何か」、各国が教育政策を考える際に参考になる共通のフレームワークを検討するプロジェクト(「Education 2030」プロジェクト)が開始されています。
このプロジェクトにおいては、新たな時代を見据え、「OECD東北スクール」のような現場での実践も汲み上げつつ、OECDの実施するPISAやPIAACなどの国際調査が測定する能力の基礎となっている、いわゆるDeSeCo(Definition and Selection of Competencies)プロジェクトで定義した「キー・コンピテンシー」の見直しを検討しています。我が国としても、このプロジェクトの開始当初から積極的に参画しています。
当該プロジェクトも含め、多様な背景、異なる事情を持つ各国が集まって国際的な枠組みを検討する際、我が国の事情も踏まえて設計されることが望ましいことはいうまでもありません。OECDの最新の研究成果を日本国内に還元しつつ、日本の教育政策についてOECDを通じて国際的に発信していくことにつなげていくことができるよう、私としても引き続き力を尽くしていきたいと思います。

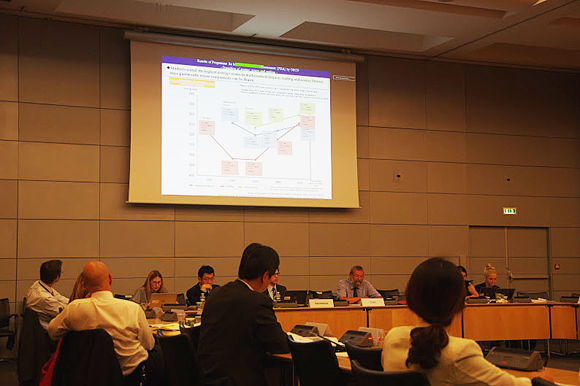
OECD会議での日本の政策紹介

