OECD邦人職員の声:加藤 貴義 環境局 気候変動政策ジュニア分析官 (ヤング・プロフェッショナル・プログラム(YPP)による採用)
2014年10月

質問1. OECDで勤務することになったきっかけを教えてください。
OECDには、2013年にヤング・プロフェッショナル・プログラム(YPP)を通じて採用されました。OECD勤務前は、英国にあるLondon School of Economic and Political Scienceで9ヶ月ほど環境経済学の勉強をしており、その間にOECDを始め複数の国際機関に応募しました。それ以前は、日本にある民間のシンクタンクで、気候変動政策の策定に関する調査や、民間企業向けの環境エネルギー関連事業に関するコンサルティングに6年半ほど携わっていました。
質問2. ヤング・プロフェッショナル・プログラム(YPP)とはどういう制度ですか。
YPPとは、所属する局(私の場合は環境局)と人事局が半分ずつ人件費を出して、正規職員として2年契約で若手(32歳以下)の人材をOECD加盟国から採用する制度で、2年に一度募集されます。このプログラムで採用された場合、A1という職位の任務と権利を与えられ、実績を積んでいくことが期待されます。3 年目以降は、同じ部署で契約を延長する人、OECD内外で別のポストを探す人と様々です。私の2年前にYPPでOECDに採用された方々は、7-8割程度が今もOECD内で勤務しているようです。
質問3. YPPの選考はどのようなプロセスですか。
大まかなプロセスとしては、書類審査、筆記試験、面接(パネルインタビュー)という流れでしたが、これは人によってかなり違うようです。パネルインタビューでは、応募ポストの職務内容に関する知識のほか、OECDが職員の業績評価を行うときの基準となるコンピテンシー・フレームワーク(Competency framework)に基づく質問も多くなされました。このフレームワークには、例えば、分析力やチームで任務を進める能力、クライアントである各国政府が何を求めているかを的確に察知する能力といった項目があります。
【参考】
●CompetencyFrameworkhttp://www.oecd.org/careers/oecdcorecompetencies.htm
●加藤気候変動政策ジュニア分析官のYPP選考プロセス
2012年10月 応募開始
2012年12月上旬 書類選考合格通知
2012年12月中旬 筆記試験受験 (小論文形式)
2013年1月中旬 筆記試験合格通知
2013年2月上旬 パネルインタビュー
2013年3月末 採用通知
質問4. どのような点が評価されて採用されたと思いますか。
私の職務は、気候変動対策に必要な資金をいかにして世界規模で動員していくかという研究をするというものですので、日本で気候変動の仕事を行っていた経験が評価されたと思います。また、応募ポストに関連しそうなOECDの論文を読み込み、自分の考えを事前に整理しておいたのが効果的だったかも知れません。加えて、自分が日本の企業で働いて得た知見(リーダーシップの考え方や、チームワークの円滑化、クライアントと関わる上での工夫など)を、コンピテンシー・フレームワークに照らして、うまく伝えられるよう準備したのはある程度効果があったと思います。
質問5. 現在の任務を教えてください。
2年間の契約のうち、最初の1年は気候変動専門家グループ(The Climate Change Expert Group)というチームで、主には気候変動対策のための資金について、国際交渉を前進させていくために、どのように技術的検討事項があるかという点についての研究を行いました 。例えば、先進国から途上国への資金の流れを把握するための方法や、またその資金によって実施された気候変動対策の取り組みが、実際にどのような効果をもたらしたかを評価する方法等について検討を行いました。
2年目の現在は、適応と開発(The Adaptation and Development team)というチームで働いています。ここでは、実際に発生した、もしくは発生しうる気候変動に対して、どう国や地域が適応していくのか、また政府がそのための計画を策定する上で、数ある政策の選択肢にどのような基準や方法で優先順位をつけていくのかという研究を行っています。
質問6. これまでで印象に残った仕事は何ですか。
特に印象が残っているのは、2013年に主担当者 として携わった、気候変動対策のための資金の動員に関する2つのレポートの作成です。「資金」というテーマは、携わっている部署が多く、作成に当たって環境局内外の様々な分析官と連携しながらレポートを作成いたしました。またOECD事務局以外にも各国の交渉官と国際会議の際に面談して意見交換を行ったり、世界中の様々な専門家と電話会議や面談を通じて議論を交えながら執筆を続けました 。またパリのOECD本部でも日々様々な会議が開催されていますので、そのような場で新たに専門家と出会い、意見交換をすることもあります。
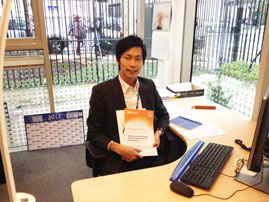
【参考】関連記事
「ボン会合特別インタビュー」(地球環境戦略研究機関(IGES))
http://www.iges.or.jp/jp/climate/201407_interview.html
「途上国のための気候変動資金動員のあり方」(エール大学ビジネスと環境センター)
http://cleanenergyfinanceforum.com/2014/09/05/designing-climate-finance-for-the-developing-world/
質問7. 実際にOECDに勤務されて、その魅力や困難は何ですか。
国際色豊かな職員が、自身の知的貢献によって世界が抱えている問題に貢献しようと、切磋琢磨し合いながら努力を続けているという点に魅力を感じています。比較的大きな組織の常として、どうしても組織の壁というものはある程度存在しますが、私が知る限り環境局はそれでも積極的に他者に情報や意見を提供し、お互い協力し合っていこうという雰囲気が強い部署だと考えております。困難というほどではありませんが、以前携わっていた国際交渉に関する研究は、各国の政治的な利害が対立しやすい分野もありましたので、用語の選び方、議論の組み立て方等は、上司とともに気を配りながら進めました。

質問8. 日本人がグローバルに活躍する上で求められる力、また潜在力は何だと思いますか。
日本人はやはり丁寧に仕事をするという点や、段取りを整える計画性、感謝の気持ちを素直に表現して伝えるという点で、チームや課の仕事をスムーズに進める力に長けた人が多いと考えています。他方で、私自身もそうですが、母国語以外ですばやく議論し、多様なステークホルダーに対して建設的な意見を提示していくというのは、ある程度語学力があっても多くの日本人にとっては容易ではないと思います。ただこれは間違いなく求められる力ですので、しっかり磨いていく必要があると考えています。
質問9. OECDを目指す若い方々にメッセージをお願いします。
国際機関で働く多くの人々が仰る様に、自分の専門性を磨くことはとても重要だと思います。加えて、期限付きの契約の中で、漠然とした将来の不安を抱えつつも、自分の価値を高めるために良い仕事をし、その成果を周りにきちんと伝えていくという精神力や行動力も必要だと感じています。それでも、ここで働く多くの職員はそれぞれの分野での専門家として、世界中の政策決定者の役に少しでも立ちたいと日々研究その他の業務を進めており、こうした環境で働けることに私自身も大きな喜びとやりがいを感じています。
