OECD邦人職員の声:加藤静香 OECD教育・スキル局 分析官(JPO派遣)
2018年11月
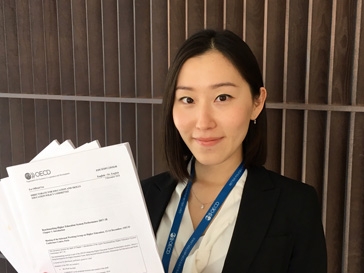
質問1. どのような経緯で今のポストに 就かれたのか教えてください。
JPO制度に応募した当時、私はイギリスの大学院の修士課程に在籍していて、高等教育制度・政策について学んでいました。大学院でたくさんの文献を読み、情報を整理し、答えを探していくプロセスに面白味を感じ、修士課程修了後も同じような経験をできないかと考えていました。博士課程への進学も検討していましたが、1つのトピックに焦点をあてて深く堀り下げていくというよりも、ある程度の幅広さを保ちながら、高等教育についてもっと知りたい、そう思っていました。
丁度その頃にOECDで高等教育に焦点を当てた新しいプロジェクトが始まったことを知り、まさに自分が求めていた仕事だと感じました。プロジェクトメンバーになるための手段を複数検討する中で、外務省のJPO制度を知り、高等教育プロジェクトに参加できるかはわかりませんでしたが、希望を託して応募するに至りました。
質問2. 現在の任務、そしてJPOというお仕事について、どのような毎日を過ごされているか教えてください。
有難いことに、希望していた高等教育プロジェクト「Enhancing higher education system performance(高等教育制度のパフォーマンス向上事業)」にJPOとして参加させていただいています。プロジェクトについて簡単に言うならば、OECD加盟国の高等教育制度のパフォーマンスを向上するため、現時点でのパフォーマンスを各国間で比較し、他国の成功例から学びあおう、というものです。
OECDには様々な職種がありますが、私は分析官という職についています。同じ分析官でも参加するプロジェクトによって仕事内容は大きく異なります。私の仕事について申し上げますと、大学院での経験にとても近く、学術文献や政策報告書を読みながら報告書を作成しています。したがいまして毎日の業務の大半はデスクワークに費やされます。具体的には、500ページを超える報告書を数人の同僚と分担して書き上げています。熱中していると誰とも話すこともなく1日を終えてしまう可能性もあるほどに、個々人の仕事は明確に割り振られています。しかし私のチームではチーム間のコミュニケーションを大切にしており、定期的に全員でランチへ行ったり、お互い声を掛け合ってコーヒー休憩を取ったりしています。夏にはチームの皆でピクニックを楽しみました。

質問3. JPOとして勤務されていて、特に苦労したことや困ったことなどを教えて下さい。
報告書の作成が終盤に差し掛かっていたタイミングで、40ページの報告書のうち15ページを削除することになったという経験があります。締切の数日前だったこと、削除になった部分はチーム全員で事前に同意していた内容だったこと、新しいテーマで15ページを書き直すことになったことから、上司がその決断をしたときにはとても驚きました。そして、自分の書いた成果物の質が低かったために削除になったのではないかと、落ち込みもしました。
しかし時間が経過するにつれて、私の職場ではこれは決して珍しいことではないことに気が付きました。私の上司も含む、私の同僚のほとんどが同じ経験をしていたのです。
大事なことは、私たちのプロジェクトへ出資している国にとって一番必要な情報は何か、出資国にとってのより良い報告書とは何かを終始念頭に置きながら仕事をすること、そして、締切が近いからといって「とりあえず」で仕事をしないこと、 その2点にあると思います。私の上司や同僚は、出資国にとって一番大切なことは何か、ということを常に考えながら、変化を厭わず仕事をしています。 私はそんな彼らと仕事できることを心から誇りに思います。
質問4. « 高等教育制度のパフォーマンス向上事業»、とは具体的にいうとどういうことなのでし ょうか?
高等教育とは、日本でいうならば、大学、大学院、短期大学、専門学校などを指します。世の中が目まぐるしく変化していく中で、高等教育制度・政策はどうあるべきなのか、という問題について様々な国で議論がなされています。
そこで、OECDのような国際機関に求められるのは、政策提言です。ここでいう政策提言とは、1.各国の高等教育制度・政策を比較し、それぞれの優れている点、改善余地のある点を検討していくこと 2.各国の成功例を共有すること、以上の2点であり、それがつまりは私の参加しているプロジェクト「Enhancing higher education system performance(高等教育制度のパフォーマンス向上事業)」です。
各国政府は高等教育に対し、経済的、社会的な期待をもっています。例えば、高等教育の拡大は経済全体の労働生産性向上に繋がるという議論がなされています。また、高等教育修了者は就職率、収入の面で中等教育修了者を上回るという点において、個人的なメリットもあると議論されています。加えて、多くのOECD諸国で格差が広がる中、高等教育は格差を縮める手段の1つとして期待されています。高等教育修了者は、中等教育修了者との比較において、生涯を通じてより健康であると報告する割合が高く、同時に政治やボランティア活動への関心が高いなどのデータもでています。
このような経済的、社会的な期待から、OECD各国は高等教育への投資額を増やし、また、より多くの人が高等教育へ進学するようになりました。例えば、日本では、大学や短期大学などの高等教育を修了した人の割合は、55-64歳の年齢グループでは40%程度であるのに対し、25-34歳の年齢グループでは60%以上に増加しています。
このような高等教育の拡大を受けて、政府は、今後どのように財源を確保するか、どう質を保つか、などの課題に直面しています。また、高等教育は労働市場のニーズに応えているか、外国人学生、社会人学生など様々なバックグラウンドを持つ学生のニーズに応えているか、といった課題もOECD加盟国で共通しています。OECD加盟国は上記のような課題に対し、十分かつ、適切な対策ができているのか、現在あるデータをもとに各国間比較をするのが、私たちのプロジェクトです。
参考:「Enhancing higher education system performance(高等教育制度のパフォーマンス向上事業)」OECDのウェブサイト http://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/higher-education.htm
質問5. 加藤さんの将来の夢はなんですか?
正直に答えると、将来のことはあまり考えていません。これまで、企業・大学での勤務、大学院留学、OECDへの就職、と環境が変化してきましたが、それは、常にその時の自分の気持ちに素直に向き合った結果です。学部生だった当時は、将来は自分のビジネスを持ちたいという思いからベンチャー企業(というには少し大きいのですが)に就職し、営業やマーケティングに従事しました。しかし、実際にビジネスの現場で仕事をする中で、自分のしたかったことはビジネスではなかったかもしれないと感じるようになり、大学に転職しました。その後もっと勉強がしたいと感じイギリスの大学院に留学したわけですが、その時の気持ちを常に優先してきたことで、フランスで分析官という想像もしなかった機会に巡りあうことができました。ですから、はっきりとした将来の夢があるというよりは、これからも自分の気持ちに素直に、大きな変化も厭わずに生きていきたいと思っております。
国際機関は任期付きでの採用が多く、不安定なところが一般的にはデメリットと思われているかもしれません。しかし可能性があふれているという意味では大変面白く、胸が高まるのを感じます。

質問6. 最後に、これから国際機関で働きたいと考えている方々に対して、こういう経験を積んでおいたほうが良い、というメッセージはありますか?
国際機関で働きたい方、というよりは、私と同じように、国際機関で分析官の職に就きたい方へ限ったメッセージになってしまうことを予めご容赦ください。
まず第一に、大学・大学院での勉強をしっかりすることだと思います。私の同僚の半分以上は博士号保持者です。そういった人たちと渡り合っていくには、定量・定性データを正しく読み解く力、専門分野の知識が必要です。私は学部生の頃、お世辞にも真面目な学生とは言えなかったのですが、その時にしっかりと勉強しておくべきだったと後悔しています。あとは、ジュニアのポスト(JPO含む)に限って言えば、学生時代に良い成績を取っておくことはマイナスにはならないと思います。学術論文の出版経験のない私にとって、大学院での成績は自身の能力を示す1つの指標になりました。
職務経験については、様々な可能性があるので一概には言えませんが、私の職場では、大学・研究機関・政府機関の出身者が多いです。
高い英語力は必須ですが、ネイティブでないからと悲観する必要はありません。英語で専門的な文章が書け、自分の思っていることをしっかりと伝えることができれば仕事はできます。少なくとも私は帰国子女ではありませんし、2年間のイギリス大学院留学が唯一の海外経験ですが、今のところ大きな問題なく働けています。
また、一般的に国際機関というと英語以外の外国語が重宝されると言いますが、私の今のプロジェクトでは仕事の評価には大きく関係しません(OECD本部はフランスにありますが、私のチームではコミュニケーションは全て英語です)。とはいえ、政策報告書のような政府文書は、英語に翻訳されないこともあります。そういった場面で、外国語は役に立ちます。例えば、今のプロジェクトでは、時に、エストニア語、オランダ語、ノルウェー語の政府文書を読む必要があり、翻訳ソフトウェアを片手に乗り切っていますが、これらの言語のいずれかでもできたら仕事のパフォーマンスが向上すると感じます。
