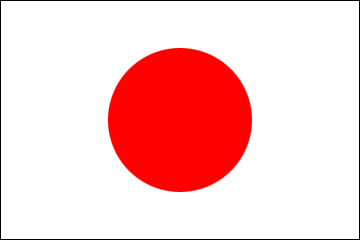OECD邦人職員の声:表 将幸 OECD公共ガバナンス局 インフラ・公共調達政策部 公共調達政策課 政策分析官
2023年3月
質問1.表さんのご専門である、公共調達(public procurement)の役割について教えてください。
私は公共ガバナンス(政府の行政能力)制度分析・改革に従事しており、特に、政府の財政に関わる公共財政管理(予算制度、税制度、会計制度、監査制度等)の中のPublic procurement(公共調達)、公共投資、地方財政(収支分析や政府間財政移転制度)などにこれまで関わってきました。現在、OECDでは公共調達制度分析及び改革支援を担当しています。
官公庁は、我々が納めている税金を使って、公共の建物を建設したり、物資を調達したりする際、主に民間の会社と契約を結んでいます。そして一定の基準(threshold 閾値と呼ばれています。)以上の価格又は事業規模の場合には原則として入札を実施しています。これを公共調達(又は政府調達)と呼んでいます。公共調達は公平性、透明性、迅速性、効率性などを確保するため、関心のある業者は誰でも参加できる競争入札を原則としなければいけません。
公共調達をする際、契約に至るまでには、1.入札までの準備段階(調達対象物の市場調査や調達上の入札条件確定等)、2.入札段階(業者への入札公告、入札評価や落札業者決定作業等)、3.契約管理段階(契約後から完了までの進捗管理、修正契約、支払い手続等)の3つのプロセスを得ることになります。
調達カテゴリーは大きく物資(goods)、役務(service)、工事(works)に大きく分類され、public procurement(公共調達)のpublicは各国の定義によるものの中央政府のみでなく、地方政府や公益法人も含みます。例えば、国立病院を例にとると、病院の建物という規模の大きいものから、医療機器、薬物、針などの医療器具、病院内の清掃サービス契約など多岐に渡ります。また、対象には、防衛省の軍事品という国家機密事項に係るものも含みます。また、コロナ危機において、各国政府がワクチンやマスク等を緊急調達しましたが、これらも公共調達の枠組みでなされたものです。日本では「アベノマスク」の元、厚生労働省が複数業者と契約締結してマスクを調達したこともまだ記憶に新しいと思います。
公共調達は、OECD諸国GDPの12.6%(メキシコ4.7%~オランダ19.6.%)、EU諸国GDPの14%を占め、経済上のインパクトが非常に大きい政府活動です。また、同時に、腐敗・汚職に最も脆弱な政府活動とされています。昨今では、公共調達の占める経済規模から、Strategic Procurement(戦略的調達)の主流化が欧州を中心として公共調達における主要課題となっています。Strategic Procurementとは、従来のように物資をただ調達(これを調達のPrimary objectiveと呼んでいます。)するのみでなく、政府の諸政策を推進する手段として公共調達を活用(これを調達のSecondary objectiveと呼んでいます)することを指します。具体的には、環境、中小企業支援、イノベーション推進、社会政策(ジェンダー等)、責任ある企業行動(RBC)などの政策が対象となっています。例えば、環境政策推進のために環境に優しい商品を積極的に購入する、多くの国で全企業の99%を占める中小企業がより入札に参加できるように契約単位(ロット)を分割する、社会的責任の一環でILO協定(児童労働禁止、雇用機会の平等)を遵守する企業のみ入札に参加できるようにしたり、契約後の生産段階でのモニタリング(労働搾取が行われていないか等)を契約上の条件とするなど、様々なアプローチがあります。Strategic procurementは、国連のSDGs(持続可能な開発目標)においては、「12.7 持続可能な公共調達(SPP: Sustainable Public Procurement)」として認識されています。
質問2.当分野に興味をもたれ、ご専門にしようと思われたのには何かきっかけがありましたか?
小学生の頃から南米、特にペルーに興味があり、大学もスペイン語学科に入学しました。大学3年の時にペルーに滞在した折、貧困、インフラの脆弱性、犯罪など日本で生活するのとは全く異なる状況に遭遇しました。また、日本へ帰国した翌日にアメリカで同時多発テロ事件が発生し、その原因は世界が抱える貧困などの問題が原因ではないのかと考え、国際協力に強い関心を抱くようになりました。
大学卒業後は8年間、外務省やJICAが実施するODA(政府開発援助)の調達・案件監理業務を担当する調達代理機関で働きました。質の高い国際協力を実現するために、開発途上国の政府が必要としている資機材やサービス(輸送・設計・施工など)の調達業務を途上国政府に代わって実施している機関でした。 その8年間はアフガニスタンやボリビアに長期滞在するなど貴重な経験をいただき、この経験は今振り返ってもその後の仕事の基礎を築いてくれるものでした。途上国政府と仕事をする中で、政府の行政能力(特に財政分野)が案件実施に影響を与える事態に多々遭遇したので、ガバナンス、特に公共調達を含む公共財政管理の政策分析・提言業務に興味を持ちました。
質問3.OECDの公共ガバナンス局公共調達政策課の役割について教えてください。
私の所属するOECDの公共ガバナンス局公共調達政策課では、公共調達制度に関する以下の業務を管轄しています。
- 2015年に採択された「OECD公共調達に関する理事会勧告」
 の加盟国実施支援と実施状況調査(実施報告書
の加盟国実施支援と実施状況調査(実施報告書 は2019年に出版)
は2019年に出版) - OECD加盟国を中心とした公共調達制度の比較分析(例えば、公共調達を通じた環境政策支援
 (2015年)、イノベーション支援
(2015年)、イノベーション支援 (2017年)、中小企業支援
(2017年)、中小企業支援 (2018年)、コロナ危機対応
(2018年)、コロナ危機対応 (2020年)、RBC
(2020年)、RBC (2020年)、ジェンダー
(2020年)、ジェンダー (2021年)等)
(2021年)等) - 各国の公共調達政策分析・改革支援に係るコンサルティング業務
- OECD加盟国の公共調達に関する統計収集(隔年でGovernment at a Glance
 発行)
発行) - Working Party of the Leading Practitioners on Public Procurement(公共調達作業部会)の年間フォーラム「Procurement Week」開催(公共調達制度に関するOECD加盟国の年間会議)
- 公共調達制度の国際標準分析ツールであるMethodology for Assessing Procure-ment Systems (MAPS)
 の事務局運営
の事務局運営
公共調達政策課が帰属する公共ガバナンス局では、各国政府を対象としたコンサルティング業務のシェアが圧倒的に多く、クライアントである各国政府へ公共調達分野での政策分析及びそれに基づいた行政改革実施を実施しています。各案件の実施予算は他の国際機関(EUや国際開発金融機関)、第三国、要請政府からの拠出等様々ですが、EU諸国に関してはEU (European Union:欧州連合)の政策執行機関であるEC (European Com-mission:欧州委員会)からの拠出がほとんどです。公共調達の分野では、日本でもよく知られている外資系会計コンサルの欧州オフィスが担当していた公共調達改革案件を引き継ぐことも多いです。その意味ではOECDの局で最も民間コンサルに近く、かつ、最もOECDらしくない局といえるかもしれません。私自身も各国政府をクライアントとしたコンサルティング案件が日々の業務のほとんどを占めています。新規案件開拓・受託のためのプロポーザルを準備し、クライアントである各国政府及びEC等の資金拠出機関(ドナー)と協議することも重要な業務となっています。
また、各国の案件内容は様々ですが、公共調達制度を軸として、2015年に採択された「OECD公共調達に関する理事会勧告」 で確認された健全な公共調達制度に欠かせない12の柱に関連します。例えば、すでに述べたstrategic (sustainable) public procurement(環境、中小企業、イノベーション、社会政策、RBC支援等)、公共調達の専門職化(能力向上)、反汚職政策、電子調達、リスクマネジメント、KPI、競争力向上、中央・地方分権化、情報公開制度、市民参加など様々です。
で確認された健全な公共調達制度に欠かせない12の柱に関連します。例えば、すでに述べたstrategic (sustainable) public procurement(環境、中小企業、イノベーション、社会政策、RBC支援等)、公共調達の専門職化(能力向上)、反汚職政策、電子調達、リスクマネジメント、KPI、競争力向上、中央・地方分権化、情報公開制度、市民参加など様々です。
図:「OECD公共調達に関する理事会勧告」 (2015年)における健全な公共調達制度の12の柱
(2015年)における健全な公共調達制度の12の柱

質問4.現在の担当業務について教えてください。
現在は、欧州(特にバルト諸国及び旧ユーゴスラビア諸国を中心としたバルカン諸国)及びラテンアメリカの約15カ国の公共調達政策分析及び改革に係る案件を担当しています。前項で述べた通り、公共調達制度を軸としつつも各国ごとに案件内容は大きく異なります。
私が担当している国を例に取ると、欧州ですと、リトアニア(公共調達の専門職化 、中央集権化
、中央集権化 )、クロアチア(公共調達を通じたイノベーション支援)、スロベニア(調達市場競争向上分析、地方分権)、ブルガリア(公共調達専門職化)、エストニア(strategic procurementを促進するための公共調達専門職化)、マルタ
)、クロアチア(公共調達を通じたイノベーション支援)、スロベニア(調達市場競争向上分析、地方分権)、ブルガリア(公共調達専門職化)、エストニア(strategic procurementを促進するための公共調達専門職化)、マルタ (リスクマネジメント、KPI、公共調達専門職化)、ギリシャ(ICT調達制度)、スロバキア
(リスクマネジメント、KPI、公共調達専門職化)、ギリシャ(ICT調達制度)、スロバキア (入札評価制度)、全般的な公共調達制度分析(スペイン、セルビア、アルバニア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、モンテネグロ、北マケドニア、チェコ)。ラテンアメリカですと、チリ(公共調達専門職化)、メキシコ
(入札評価制度)、全般的な公共調達制度分析(スペイン、セルビア、アルバニア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、モンテネグロ、北マケドニア、チェコ)。ラテンアメリカですと、チリ(公共調達専門職化)、メキシコ (電子調達、公共調達専門職化)、コロンビア(入札参加に係る業者登録制度)、ペルー(反汚職政策・リスクマネジメント)、コスタリカ
(電子調達、公共調達専門職化)、コロンビア(入札参加に係る業者登録制度)、ペルー(反汚職政策・リスクマネジメント)、コスタリカ (全般的な公共調達制度分析、競争向上分析)など、政策分析・改革支援対象となる分野は様々です。
(全般的な公共調達制度分析、競争向上分析)など、政策分析・改革支援対象となる分野は様々です。
また、隔年で公共ガバナンス局が発行しているOECD諸国のガバナンスに係る様々な統計を掲載するGovernment at a Glance の2021年度版発行に係るOECD諸国の統計集計や章の執筆なども担当しました。Government at a Glanceには地域版もあるのですが、例えばラテンアメリカ版は米州開発銀行との共同プロジェクトとして現在進行しています。公共調達に関する研修業務にも大きく関与しており、例えば、国際通貨基金(IMF)からの要請でアラブ諸国向けの公共調達に係る研修プログラムの講師を担当するなど、業務内容は実に様々です。
の2021年度版発行に係るOECD諸国の統計集計や章の執筆なども担当しました。Government at a Glanceには地域版もあるのですが、例えばラテンアメリカ版は米州開発銀行との共同プロジェクトとして現在進行しています。公共調達に関する研修業務にも大きく関与しており、例えば、国際通貨基金(IMF)からの要請でアラブ諸国向けの公共調達に係る研修プログラムの講師を担当するなど、業務内容は実に様々です。
要は公共調達を切り口として様々な分野に対応できる必要があるのですが、テーマ別で私が特に力を入れているのが、公共調達業務の専門職化です。
質問5.公共調達業務の専門職化について教えてください。
昨今の各国の公共調達制度改革重点分野の一つとして、公共調達専門官の専門職化(能力向上)が挙げられます。公共調達業務の遂行には、公共調達法や関連法規等の法律、調達条件確定のための市場調査、入札評価基準(評価点算出式など)などのハードスキルから、プロジェクトマネジメントや契約業者との交渉などのソフトスキルに至るまで幅広い専門知識とスキルが要求されます。特に、昨今の公共調達はstrategic (sustainable) procurementを通し SDGsに貢献する政策ツールとして認識されているので、調達専門官には一層の専門性が求められます。しかしながら、法律や会計などと違い、公共調達を専門職とみなしているのはOECD諸国で38%(2020 年末時点)です。調達業務は経理・財務課の職員が本業の傍ら片手間で実施する業務と位置付けられるのが現状です。国家規模での資格認定制度(Certification Framework)を導入している国もまだまだ世界で僅かです(OECD諸国で35%)。
私が2018年に公共調達政策課で初めて担当した案件の一つが、リトアニアにおける調達業務の専門業務化に係る国家資格制度構築や調達能力向上研修計画策定及び実施でした。本案件をもとにリトアニア政府は法改正等を経て、昨年2022年7月より念願の公共調達国家資格制度を開始するに至りました。
2020年12月には、EU加盟国の公共調達専門職化を推進すべく、ECがEuropean compe-tency framework for public procurement professionals(通称:ProcurCompEU) を開発しました。その中で提供されている公共調達専門官に必要とされる30の主要能力・スキル(ハード19及びソフト11 )を示したコンピテンシー・マトリックス作成においては、リトアニア案件で私が提示した資格制度構築に係るカリキュラム等も大いに参考にされました。ECはProcurCompEUがEU加盟国のみでなくEU圏外でも幅広く活用されることを期待しています。このような経緯から、ECからの要請を受けて、ProcurCompEUを世界各国の公共調達専門職化改革に活用するパイロット案件
を開発しました。その中で提供されている公共調達専門官に必要とされる30の主要能力・スキル(ハード19及びソフト11 )を示したコンピテンシー・マトリックス作成においては、リトアニア案件で私が提示した資格制度構築に係るカリキュラム等も大いに参考にされました。ECはProcurCompEUがEU加盟国のみでなくEU圏外でも幅広く活用されることを期待しています。このような経緯から、ECからの要請を受けて、ProcurCompEUを世界各国の公共調達専門職化改革に活用するパイロット案件 をECの要請によりOECD が2021~2022年にかけて実施しました。本パイロット案件には6か国(ニュージーランド、イタリア、チリ、アイルランド、アイスランド、コスタリカ)が選定され、私はチリとコスタリカを担当しました。チリ財務省とは、チリ国内にすでに存在していた公共調達専門官の国家資格制度及びコンペテンシー・マトリックスをProcurCompEUをもとに一新し、短期間で行政改革につなげることにできたのが印象的です。
をECの要請によりOECD が2021~2022年にかけて実施しました。本パイロット案件には6か国(ニュージーランド、イタリア、チリ、アイルランド、アイスランド、コスタリカ)が選定され、私はチリとコスタリカを担当しました。チリ財務省とは、チリ国内にすでに存在していた公共調達専門官の国家資格制度及びコンペテンシー・マトリックスをProcurCompEUをもとに一新し、短期間で行政改革につなげることにできたのが印象的です。
また、各国の公共調達政策担当官等と日々協議をする中で、公共調達専門職改革を推進するための簡潔なフレームワークを提示する政策提言書があると有用と考え準備したペーパーProfessionalising the public procurement workforce: A review of current initiatives and challenges が2023年1月末に出版されました。予算もなく私が業務の傍ら初版は3日で執筆したものでしたが、各国政府や関係国際機関からポジティブなフィードバックを多くいただけ企画してよかったと思っています。また、本ペーパーは、公共調達専門職化の新規案件策定にもすでに使用しており、現時点で新たに4か国と公共調達専門職化案件を形成できそうです。今後もこの分野を通して、各国における公共調達及び公共調達専門官の地位向上に貢献できればと思っています。
が2023年1月末に出版されました。予算もなく私が業務の傍ら初版は3日で執筆したものでしたが、各国政府や関係国際機関からポジティブなフィードバックを多くいただけ企画してよかったと思っています。また、本ペーパーは、公共調達専門職化の新規案件策定にもすでに使用しており、現時点で新たに4か国と公共調達専門職化案件を形成できそうです。今後もこの分野を通して、各国における公共調達及び公共調達専門官の地位向上に貢献できればと思っています。
質問6.OECDで働くことの魅力について教えてください

Public procurement(公共調達)に限ったことではありませんが、各国政府の改革のお手伝いができることです。OECDで決定することには原則拘束力がなく、あくまで提言にとどまりますが、それでもOECDの提言が政府の改革に実際に取り入れられることは多く、とても嬉しいことだと思っています。調達代理機関 での8年間は調達のオペレーションに関わるのが主な仕事でしたが、現在は、その実務経験を活かし各国の調達制度の分析をするなど、問題を国家レベルで考えることができるのは非常に大きな魅力だと思います。
また、各国のハイレベルの政策担当者と直接意見交換できるのもOECDで働く上での醍醐味だと思っています。実際、多くの案件で各国のカウンターパートはその国の公共調達政策のトップであることが多いです。それゆえに、有益な情報や政策を提言できるよう、日々勉強しなければいけないのも事実です。
OECDでは政策分析・提言書を書くことが求められますが、案件実施の過程で執筆した政策提言書を出版できることもOECDで働くことの魅力だと思います。私も毎年約5-10件近い政策分析書をOECDを通して出版しており、私自身のキャリア形成においてもとても有意義な経験になっています。
また、ヨーロッパでの生活もOECDで働くことの大きな魅力だと思っています。私はこれまでアフガニスタン、ボリビア、アメリカ(ワシントンD.C.)、ペルーに住んだことがありますが、これらの国々と比べても、フランス(パリ)からは近隣諸国への旅行がとても容易にできます。私は現在まで41カ国のヨーロッパ諸国を訪れ、未踏地は5カ国(ノルウェー、モルドバ、ロシア、ウクライナ、ベラルーシ)になっています。ヨーロッパ旅行の過程で旧ユーゴスラビア諸国に興味を持ち、セルビア語(クロアチア語、ボスニア語、モンテネグロ語もほぼ同様の言語)の学習を開始し、私の希望で現在はクロアチアやスロベニアなどの旧ユーゴスラビア諸国の案件にも従事しています。
質問7.これからOECDで働きたい方へのメッセージ
既述の通り、OECDでの業務は、(しっかりとした提言をすれば)国の政策を変えるほどのインパクトをもたらすことができ、非常にやりがいのある仕事です。政策提言に興味のある方は積極的に応募していただきたいと思っています。特に、公共ガバナンス局は300人ほど職員がいる中で、日本人職員は私一人ですので、ガバナンス(行政改革)分野での経験がある方はぜひ挑戦していただきたいと思います。ただ、空席公募ですとどうしても競争率が高くなるため、外務省が実施しているJPO制度を活用されることをお勧めしたいと思います。実際、私もJPO制度で公共ガバナンス局に派遣いただき、JPO終了後に空席公募を経てOECDの正規職員に採用され、2年ほど前より契約期限なしのopen-ended(日本でいう終身雇用に近い)契約に変更いただき現在に至ります。
OECDで働くにあたっては、他の多くの国際機関と同様、外国語(可能であれば英語+数カ国語)で会議やプレゼンテーションで自分の意見を論理的かつ明快にはっきりと表明でき、また、論理的に分析報告書を書ける能力は不可欠だと思います。OECDは各分野のハイレベルの政府担当官と直接仕事をするものなので、当然その分野での高い知識とそれをその分野の専門家と討議し、共に政策協議できる能力が必要だと思います。選考過程における筆記試験や面接でも当該分野における専門知識やライティング能力が非常に厳しく問われますので、準備の際には募集部署の出版物をできる限り読み込み、事前に想定問答を準備しておくことをお勧めします。特に入念な準備なしでは筆記試験を時間内にすべて回答して通過するのは難しいと思います。
ご経験を活かせるポストがあれば、ぜひ積極的に応募していただきたいと思います。

(写真)部署の同僚とセルビア料理店にて(8人8国籍!)