OECD邦人職員の声 : 根本 拓 OECD貿易農業局・ジュニア政策分析官
2019年12月
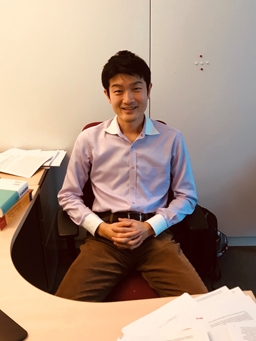
執務室の筆者
1. 担当業務
私は現在、貿易農業局(Trade and Agriculture Directorate)のジュニア政策分析官として勤務しています。私はもともと貿易に関する国際ルール(国際通商法)を専門とする弁護士として日本で働いており、OECDではこの専門性を活かして貿易政策の分析に関与しています。
私が担当している貿易のイシューは主に、政府補助とデジタルトレードです。前者は、政府が企業に対して供与する補助金(贈与、減免税、低利子融資等)によって国際経済が歪められていることにどのように対処すべきかという問題であり、米中の貿易をめぐる緊張関係の大きな要因ともなっています。後者は、デジタルテクノロジーの発展に伴い貿易の在り方も変化してきているところ(たとえば昔はCDを輸入して聞いていた外国の音楽を今はインターネット経由で入手できる)、これに伴って新たな貿易ルールが必要とされている分野です。日本政府も2019年6月のG20 大阪サミットでこの問題を大きく取り上げ、デジタル時代の新たな貿易ルール作りをリードする姿勢を示しました。
OECDで私は、こういった貿易の分野で最もホットなイシューについて現状を分析し、将来これらの分野でどのような政策が世界においてとられるべきかを提言するということに取り組んでいます。
2. 半導体報告書の発表
私がOECD事務局で働き始めたのは2019年8月でしたが、それ以来注力してきたプロジェクトとして半導体産業に対する政府補助についての調査案件がありました。世界各国にとって、スマートフォン等のデジタルデバイスにも用いられる半導体の産業としての重要性が増してきており、また半導体の開発生産には多額のコストがかかることから、一部の政府は大規模な政府補助により半導体産業を育成しようと試みています。しかし、このような政府補助は、企業間の公正な国際競争を阻害し、貿易を歪めるものとなり得るため、各国から懸念が示されていました。OECDはこの問題に着目し、各国政府からどのような補助がどのような形で半導体産業に出されているかという実態を調査し、それをもとに、既存の国際貿易ルールをどのようにアップデートするべきかについての提言を100ページ超の報告書にまとめ、2019年12月に発表しました。
私は、政府補助の実態調査をもとに、そこに適用される既存の貿易ルール(WTOルール)を整理し、その上で既存の貿易ルールが十分に規律できないであろう問題領域を特定し、それに対処するために必要となる新たなルールについて検討しました。
このレポートは国際貿易における最先端の問題を扱ったというだけではなく、その分析の深さや政策的インプリケーションの重要性という点において大きなインパクトを持ち得るレポートになっており、すでに多くの人に読まれ、メディアでも取り上げられています。
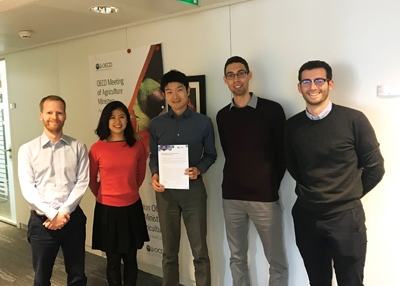
半導体調査案件チームメンバーと
3. OECDで働くことの魅力
OECDで働くことの魅力は第一に、自分の専門分野の最先端のイシューについてじっくりと取り組み、各国の政策にインパクトを及ぼし得る仕事ができることです。弁護士時代は特定の依頼者の利益を最大化するために、短い期限の中で目の前の仕事を一生懸命こなしていました。一方でOECDは、「依頼者」たるメンバー国と協議しながら、OECDとして取り組むべき中長期的な世界の課題を特定した上で、関連文献やデータを長い時間をかけて慎重に分析し、その成果を世界中で読まれるレポートにして発表し、ときにはガイドラインという形で世界が進むべき方向性を示します。このようにグローバルな課題にじっくり取り組み、そのうえでより良い国際社会を実現するための政策を提言できることは、ほかの場所にはない魅力といえるでしょう。
第二に、OECDには、経験や専門性、国籍などの点で多様なバックグラウンドを持つ職員がいます。例えば上記の半導体チームはエコノミスト、投融資の専門家、私のような法律家が一つのチームを構成することで、多角的な視点から問題を分析することができ、最終的に質の高いレポートにつながったと思っています。法律家である私にとって、エコノミストから世界がどう見えているのかを知り、それをどうルールに落とし込むかを一緒に議論することは、新たな視点や発見を提供してくれるものであり、この環境は貴重だと感じています。

普段、活発に議論が交わされるカフェテリア
4. これからOECDで働きたい方へのメッセージ
私は公募に応募する形でOECDに入りましたが、結果はともかく選考プロセス自体が、国際社会における私の強みはなんだろうかということを徹底的に考える機会になりました。この選考プロセスは神経が磨り減るものではあるのですが、応募することから全ては始まるというだけではなく、選考プロセスを若いうちに数多く経験することによって、日々の生活において、どう自分の強みを磨き弱みをカバーするかということへの意識が高まり、結果はどうであっても自分の成長につながるように思いました。応募を迷っている方がいれば、まずは結果を気にせずに応募することをお勧めいたします。
とはいえ、すでに日本で組織に所属している方にとってOECDに有期契約(若い職員は基本的に最初は有期契約です)で勤務することはリスクが伴うのも事実だと思います。本来であれば、OECDで数年勤務してその経験を日本に還元し、その後また国際機関により高いポジションで戻っていくようなキャリアパスが現実的なものとなるべきだと思いますが、今の日本の硬直的な労働市場の中ではそれが難しい部分もあろうかと思います。しかし、日本の若い人材の潜在力を最大限生かすためには、若手がいったん組織を離れて海外で武者修行をし、個としての力を高めてまた同じ組織に戻ってくることが広く許容されるべきであり、今後の日本の国際競争力を高めるために、日本においてそういった理解が広がることを願っています。
