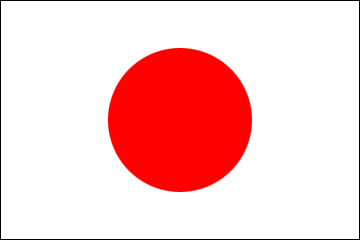OECD邦人職員の声:山田 由美香 OECD開発センタ-事務局・政策分析官
2020年2月

OECD本部
現在の業務
2018年6月より、質の高いインフラ投資推進プロジェクト、政策分析官兼プロジェクトマネージャーとしてOECD開発センターで勤務しております。OECD開発センターは現在、30か国のOECD非加盟国及び27か国のOECD加盟国からなる組織で、途上国・新興国を交えた政策対話、知識・経験共有プラットフォームとして、途上国・新興国の経済発展、生産性向上、人々の暮らしの改善に向け、政策決定者へ分析を提供する組織です。ユニークな構成故に、同僚も多国籍で、多様なバックグラウンドを有する優秀かつ素敵な方々に恵まれ、日々和気藹々と楽しく業務を行なっております。
質の高いインフラとは、日本政府が国際機関や各国と協力しリードしている分野であり、途上国・新興国の開発戦略に沿った形で、包摂的かつサステイナブルな(持続可能な)成長につながるインフラ整備を目的とし、力強いイニシアティブを発揮しているテーマです。私のポストは2019年G20日本議長国下における質の高いインフラ国際原則策定及び実施に向けたアウトリーチを見据え、日本政府の任意拠出金により作られたポシジョンです。日本が議長国になる前の2018年は、各国のインフラ政策及び政策実施を促す制度の分析を行い、メンバー国及び専門家を交えた政策対話を通じ、途上国・新興国の抱える課題を特定・分析しました。議長国となった2019年はG20開発作業部会を通じ、国際機関・国際開発金融機関などと協働して、途上国・新興国の立場から、インプットを提供しました。G20関連業務以外にも、質の高いインフラはOECD全体の水平プロジェクトとしても動いており、開発センター代表として、他部局との協働・調整を行なっております。2020年現在、昨年策定された国際原則の普及、及び政策実施に向けた課題抽出、必要とされるツールの分析、政策対話等を行なっております。

デスクの様子
これまでの経歴とOECD勤務のきっかけ
現在は各国の優秀な開発専門家と共に仕事をする機会に恵まれておりますが、私はこれまで開発分野のみで働いてきたわけではありませんでした。そもそも環境問題解決に向けた化学研究者を目指していたこともあり、日本の大学では化学を学びました。そのうちに開発学への興味が大きくなり、同時に海外に住んでみたい、という単純な理由から、大学院進学を決め、ロンドンにて修士号を取得しました。修士号取得後、環境・開発NGO及び民間金融機関での勤務を通じ、世の中のお金の流れに疑問を感じ始めました。開発援助による途上国支援に加え、短期的利益重視の個人・機関投資家・消費者のアプローチを変え、持続的なビジネスサイクルを生み出さなくては、グローバルレベルで開発問題解決に必要とされている変化をもたらすことができないのではないか、という考えに行き着き、方向性を変え、2005年からESG(環境、社会、ガバナンス)責任投資の分野に飛び込みました。当時はまだ、日本でそういった概念が生まれ始めたばかりの時代でしたが、いわゆるCSRに対する企業の経営戦略及びパフォーマンスを評価し、投資家に投資判断となるアドバイスを行なっておりました。ロンドンを拠点に機関投資家、アセットマネージャー、保険会社、年金基金をクライアントに持ち、共に責任投資方針を打ち出し、エンゲージメント(株主行動)による経営戦略改善を指揮し、ロンドン及びヨハネスブルク証券取引所社会的責任投資インデックスのプロジェクトマネジメントも担当しておりました。気候変動を専門とし、非財務要因による企業財務へのリスクの低減、機会創出のための調査研究・アドバイザリ―業務に従事しておりました。当時から国際機関のもつダイナミックな提言力、様々な地域へのアウトリーチ力等に魅力を感じ、いつかは国際機関で働いてみたいと思いを膨らませておりました。子育てがひと段落した時期に、外務省ウェブサイトにてOECD開発センターの公募を見つけ、今に至っております。

マリオ・ペッチー二OECD開発センタ―所長と TICAD7横浜ミッションにて
現在の職務で大変だったこと
私のポストは、もともとあったポストではなく、新たに作られたものだったこともあり、チームもなく、たった一人でのスタートでした。もちろん後押ししてくれる上司はいましたが、右も左もわからない当時、誰に声をかけたらどんな情報がもらえて、自らのアジェンダを後押ししてもらえるのか、といった組織的知識を得るのに非常に苦労しました。組織内における権限構造を理解することは非常に大切で、特にOECDのように優秀な人材が多いにも関わらず、雇用が安定していない職場となると、それぞれが自らのVisibility確保に向けて必死に戦う毎日です。その中で、私のポジションのような、その他の専門家からのインプットが必須となるポストでは、どのようにインセンティブを創出し、協力を仰ぐかは日々の課題です。勤務を始めて半年経った頃、本テーマにおいて専門家会合を開催する機会に恵まれました。しかし、民間企業において会合運営の経験はあるものの、国際機関では何からどう始めていいのかわからない状態。短期間で会合のテーマを決め、コンセプトを立て、議論の軸となるペーパーを書き、専門家を選び、声をかけ、形にするまで、全てを一人でこなして行かなければならず、非常に苦しい日々でしたが、振り返るとあの経験によって、力を貸してくれる同僚と出会え、組織的な知識も増え、周りとの絆も深まった気がします。組織内で確立していないワークストリームをデザインし、運営していくのはエネルギーを要しますが、ある意味、自分のやりたいようにできる、という醍醐味もあります。その中で必要となってくるのが、同僚とより良い関係性を作っていけるか、ということに尽きると思います。専門性や分析能力、文章力も必要となる職務ではありますが、一人では完成することのできない責務であるがゆえ、コーディネーションスキルは非常に重要だと感じています。特に前述のOECD全体の水平プロジェクトでは、マンデートや優先項目の違う他部局との協働が必須であり、それぞれの専門性を生かしつつも、互いに尊重し合い、協力することが重要ですが、時にぶつかり合うことも少なくなく、効率的かつ有効なコミュニケーションを通じて平和にプロジェクトを進めていく配慮が重要な点の一つだと思います。同時に普段交わることのない他部局の優秀な方々と知り合うことが出来、それぞれの取組を知ることが出来る水平プロジェクトに参加できることは非常にラッキーだったと感じております。

息子とのパリ生活
キャリアと家庭の両立
私の目標は、キャリア形成と同じくらい、自分自身のサステイナビリティ(持続可能性)や個人としての幸せにしっかりと責任を持ち、わがままに追求していくことです。現在、9歳になる息子と二人でフランスに暮らしておりますが、夫は仕事の関係上、同居していないので、仕事との両立は正直本当に大変です。シッターさんの力を借りて、子育てとなんとか両立しておりますが、唯一の心の支えは、同様な境遇にいる同僚がたくさんいることです。悩みを分かち合い、個人としての幸せを語り合える仲間がいて、共に前を見て進んでいき、日々自分磨きを怠らない。そんな素敵な同僚達に巡り会えて、自分の悩みは小さなものに思え、前に進む力となっています。日本で従来、女性が得意とされてきた家事・育児とは、タイムマネジメントと意思決定の連続であるがゆえ、女性は男性に負けず劣らず、意思決定力、柔軟性、豊かな創造力に長けていると思います。日本の大学時代の友人女性達はまだまだ日本でのキャリアと家庭の両立で自らを犠牲にしているように見受けられます。男女問わず、個の可能性を最大限発揮できる社会になるには、女性の活躍機会推進と同等に、男性側の職場における柔軟性が不可欠であり、制度導入だけでなく、トップによる積極的な制度活用を通じた、実施促進の環境づくりが大切だと思います。こうした中で、ジェンダーの壁を越え、国際的競争力を兼ね備えた人材が能力を発揮し、国際舞台で活躍していくことを期待しております。
今後の展望
これまで、NGO、民間企業、独立調査機関、個人事業主、そして現在の国際機関といった様々な職場を経験して参りました。それぞれの職場で、組織自体の役割やキャパシティの認識と同時に、自らの強み、弱みを分析し、職場ごとに必要とされる即戦力になるための訓練をしてきました。そして一つの組織では補いきれない能力強化の必要性も身を以て感じました。年齢を重ね、守るべきものが増えていくと、リスクや変化を恐れ、動きが鈍くなりがちですが、居心地の良い場所よりも、その時その時のキャリアステージにおいて必要となるスキル、経験を積めるような、チャレンジし続ける道を選んで行きたいと思っております。