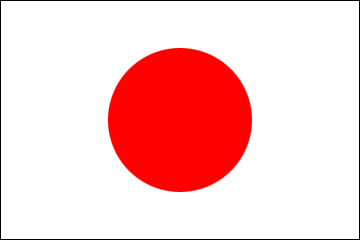OECDは三ツ星レストラン
2021年2月
OECD日本政府代表部大使
岡村 善文

「OECD」という言葉を、皆さんはどこで目にするでしょうか。新聞で「OECDの統計によれば」とか「OECDはこれこれを発表した」という記事がたびたび出てきます。統計や報告はOECDの大きな強みです。パリの本部には、約2千人の事務局職員が働いていて、その多くは加盟各国出身の、様々な分野での第一線の専門家たちです。そしてそれぞれの分野について、分析と研究を続けている。
彼ら専門家の強みは、何といっても統計や基礎情報です。これらを、各加盟国の代表部を通じて各国政府から直接得ている。わが代表部にも、これこれの数字を出してくれ、これこれの政策動向を教えてくれ、という要請が来ます。代表部はそれを東京に繋いで、政府の各省庁からの回答を得ています。それら新鮮で正確な材料を料理するのですからね。OECDの統計や報告が信頼できるわけです。よくOECDは世界最大のシンクタンクだ、と言われる。そういう大きさの面だけではなく、世界最高品質です。他のどんなシンクタンクにも、これだけの情報を集める能力はない。
それらをもとにしてOECDは分析を行い、報告や政策提言をまとめます。何よりも経済についての分析が本領です。世界経済全体を対象にして、半年に1度「エコノミック・アウトルック」を出して、先進国全体とともに各国別に経済の現状を概観します。日本の人々、とくに企業や投資家は、世界経済がどんな課題を抱えているか、日本の景気は上向くのかなど心配でしょう。だからその内容は大きく報道され、注目が集まります。また経済政策については、2年に一度各加盟国について審査が行われて、その結果を「審査報告」として纏めます。これは現状の分析だけでなく、政策にも踏み込んだ報告です。日本もその審査を受け、「対日経済審査報告書」として公表されています。それ以外の分野でも、たとえば農業、環境、雇用、ビジネス、移民、社会問題、教育などについて、同様に定期報告や、個別の課題についての特別報告が出され、それぞれの分野に関心のある人々に材料を提供します。日本では各省庁が白書を出しますね。あの国際版だと考えていただければいいでしょう。
また、加盟国各国ごとに様々な指標についての統計を、随時更新しながら一覧表にして出しています。このOECD統計は、世界中の研究者に、基礎資料を提供します。また報道記事や論説を書く人々が、その根拠として引用しています。統計というと、だいたい経済成長率とかインフレ率とか人口とか、無機質な数字を想像します。でも、OECDは独創的なデータも収集しています。例えば学習到達度(PISA)とか、幸福度指標(Better Life Index)とかです。日本の生徒は他の国よりどの教科で秀でているのか、日本人は世界の人と比べて幸福なのか、知りたいですよね。面白い数字を独自の手法で出しているのは、OECDならではの統計と言えます。
こうした統計や報告書は、OECDのHP で誰でも見ることができます。一番下の「Data」や「Publications」などに並んでいる項目をクリックすると出てきます。日本の一人当たり国内総生産(GDP)はOECD諸国平均よりも少ないんだ、とか、日本の失業率は各国に比べて格段に低いな、とか見やすい図からいろいろ分かります。報告書の一部は、日本語訳がOECD東京センターから出版もされています。
で誰でも見ることができます。一番下の「Data」や「Publications」などに並んでいる項目をクリックすると出てきます。日本の一人当たり国内総生産(GDP)はOECD諸国平均よりも少ないんだ、とか、日本の失業率は各国に比べて格段に低いな、とか見やすい図からいろいろ分かります。報告書の一部は、日本語訳がOECD東京センターから出版もされています。
OECDの強みは、証拠に基づいた分析(evidence based analysis)と言われます。偏った手法によらない正確なデータに基づいて、説得力のある報告書を作成していることです。またその時々の課題や疑問に応える研究を行っています。たとえば最近のコロナ禍の中で、その経済的影響などについて頻繁に分析を発表しています。これらを支えるのが優秀な専門家たち。OECDは、いわば吟味された新鮮な食材をもとに、腕利きのシェフが料理を作る三ツ星レストランのようなものです。時には料理にスパイスが効きすぎることもあるのですがね。