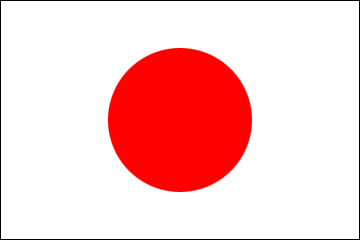OECDはゴールド免許
2021年4月
OECD日本政府代表部大使
岡村 善文

OECDがとても実務的で、有用な機関であることは説明してきたとおりです。それだけではなく、OECDにはもっと大きな意義があります。それは加盟国皆が同じ方向と目標に向かっている、「同志国(like-minded)」の国際機関だということです。つまり加盟国が、自由で開放的な市場経済、自由・民主主義、法の支配、人権尊重といった核心的価値(core values)を共有しており、そうした価値を促進することがOECDの活動の暗黙の前提になっていました。
「暗黙の」と述べたのは、実はこうした価値観は設立条約 (1961年)を見ても、どこにも書かれていないからです。設立条約の第1条には、機関の目的として(1)財政金融上の安定を維持しつつ、できる限り高度の経済成長と雇用,生活水準の向上を達成し,もって世界経済の発展に貢献する、(2)開発途上国・地域の経済の健全な拡大に貢献する、(3)世界貿易の多角的・無差別な拡大に貢献する、の3点が挙げられているだけ。あえて言えば、前文の冒頭に、経済力・繁栄は個人の自由の擁護と一般的な福祉の増進という国連の目的の達成のために不可欠だ、と述べてあるくらいです。「民主主義」や「人権」などの文言は見当たりません。
(1961年)を見ても、どこにも書かれていないからです。設立条約の第1条には、機関の目的として(1)財政金融上の安定を維持しつつ、できる限り高度の経済成長と雇用,生活水準の向上を達成し,もって世界経済の発展に貢献する、(2)開発途上国・地域の経済の健全な拡大に貢献する、(3)世界貿易の多角的・無差別な拡大に貢献する、の3点が挙げられているだけ。あえて言えば、前文の冒頭に、経済力・繁栄は個人の自由の擁護と一般的な福祉の増進という国連の目的の達成のために不可欠だ、と述べてあるくらいです。「民主主義」や「人権」などの文言は見当たりません。
しかし1961年に設立されたとき、世界は東西冷戦の只中でした。60年の歴史の中で前半30年の間、OECDは西側諸国の牙城のひとつであったのです。共産主義や国家管理の社会に対抗するために、自由経済・社会を守るという使命を背負うことになりました。第二次大戦直後の欧州は、戦争で西側経済は壊滅し、むしろベルリンの壁の向こう側の方が経済は強かった。そこに当時圧倒的な経済力を有していた米国によるマーシャルプランが、西側諸国への強烈な梃入れとなります。また資本主義が社会主義に経済的には勝っていたために、次第に欧州のOECD諸国は繁栄し裕福になりました。OECDが「金持ちクラブ」と揶揄されることがあるのは、その結果に過ぎません。自らの経済・社会運営、さらには政治的価値に自信を持った国々の集まり。それがOECDなのです。
ところが、OECDと相克していた陣営はベルリンの壁の崩壊(1989年)以降消滅し、世界経済が一体で動くようになります。OECDが信奉してきた価値は、東欧を始めとする旧東側陣営の国々にも普及するようになりました。輸送・流通手段や情報通信技術の発展、世界各地での経済統合や国際分業に伴い、経済のグローバル化が進みました。その中で、OECDはいったい何が加盟国を繋ぐ絆なのかを問い続けています。
10年前の2011年、つまりOECD設立50周年の機に、「OECD50周年ビジョン・ステートメント 」が採択されました。この中には、市場経済も、民主主義も、法の支配も、人権も、すべて基本的な価値として明記されています。今年は設立60周年なのでこの声明を見直す作業が進められています。
」が採択されました。この中には、市場経済も、民主主義も、法の支配も、人権も、すべて基本的な価値として明記されています。今年は設立60周年なのでこの声明を見直す作業が進められています。
その中で一つの課題は、いったいOECDはどこまで拡大するのか、ということです。加盟20か国で始まり、その後37か国に増えています。近々コスタリカが加盟を果たすので38か国になる見込みです。すでに欧州からルーマニア、ブルガリア、クロアチア、中南米からアルゼンチン、ブラジル、ペルーの合計6か国が加盟を申請しています。加盟国が増えればそれだけ世界に対するOECDの有用性と影響力が広がります。一方で心配も出てきます。
何より「同志国」の組織であることを前提に、OECDは特定の例外事項を除いて総意(コンセンサス)で物事を決める原則で運営されています。ということは,一か国でも反対があれば、物事が決められなくなる。加盟国数の増加とともにそうなる危惧が出てきます。誰もがOECDを第二の国連にしたくない、と考えています。国連はほぼ全世界が加盟国ですから、立場や考え方が異なり、互いに敵対する国さえあり、重要な問題に一致団結して取り組むことが難しくなっている。今のところ、価値観を共有するOECDにはそういう問題はありません。
OECD加盟というのは、経済発展や政治的安定を達成した国にとって、同志国になったとの資格認定です。免許証で言えば安全運転を証明するゴールド免許のようなもので、誇らしいですよね。私は7年前に、八王子駅前で一旦停止の標識を見落としてゴールド免許から格下げになり、不甲斐無い思いをしました。今はアジアの加盟国は日本と韓国だけですけど、今後は「ゴールド免許」認定をめざしてアジアからもどんどん加盟申請が出てくる可能性があります。これからOECDがどういう姿に変貌していくべきなのか、大きな課題となっています。