OECD邦人職員の声:池田 京 OECD教育スキル局・上級分析官
2022年7月
1. 生徒の学習到達度調査:PISA(Programme for International Student Assessment)
OECD教育・スキル局で、主席分析官としてPISAのデータ分析と報告書作成をするチームを率いています。2004年にOECD/PISA事務局にに加わり、10年ほど分析官として働いたのち、2015年より現職についています。また、分析のための国際比較可能な質の高いデータを集めるために、4年に及ぶプロジェクトサイクルを通して、様々な専門家会合を取りまとめ、80を超える参加国・地域を技術的にサポートしています。
PISA調査は、国際比較を通して各国の教育政策・実践に寄与することを目的としています。2000年に最初の調査が実施されて以来、3年おきに15歳の生徒を対象にして読解力、数学的リテラシー、及び科学的リテラシーを評価すると同時に、生徒の家庭背景、興味・関心、態度及び動機付けなどのデータも集めています。これに加え、協同問題解決能力、グローバル・コンピテンス、といった新しい分野の調査も行っています。PISAの特徴は、生徒が持っている知識や技能を、実生活の様々な場面で直面する課題にどの程度活用できるかを評価するところにあります。
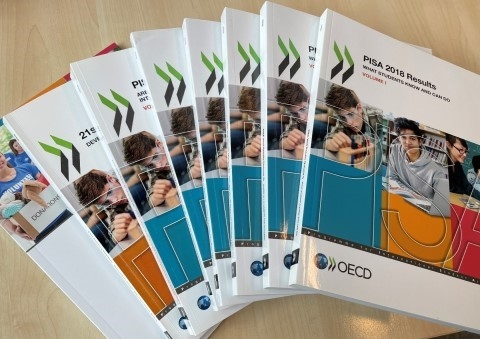
2019年12月から2022年2月の間に出版したPISA国際報告書。
2. PISA 2018年度調査の国際報告書
PISA 2018年度調査を例にとると、2019年12月に最初の調査結果を3冊にまとめて出版したのち、2020年に3冊、2021年に2冊の国際報告書を作成・出版しました。最初の3冊は、計1000ページを超えるにもかかわらず、最終的なデータを入手してから僅か数か月の間に仕上げなくてはなりません。チーム一丸となって寝る間も惜しんで取り組み、公表予定日に無事分析結果が世界各国に行き渡る様子を目の当たりにした時の、達成感・安堵は計り知れず、一緒にやり遂げたチームメンバーとの一体感は何事にも代えがたいです。
PISAのデータ分析から得られる知見を分かち合うために、様々なレベル(国際、地域、国)の会議で、プレゼンテーションをしたりパネルディスカッションに参加しています。コロナ禍ではオンランセミナーが中心でしたが、最近は対面式会議も復活しつつあり、2022年2月にはドバイ万博において開催された国際会議、またその後の大臣会合に参加しました。議題のグローバル・コンピテンスに関して、PISAのデータ分析結果及び各国の事例を提供し、国際会議・大臣会合の準備段階から関わりました。この二つのイベントには、世界各国の政府高官、実務家、研究者が一堂に集い、グローバル・コンピテンスの重要性を再確認するとともに、今後各国の教育にどのように組み込んでいくのかをより踏み込んで議論する次のステップに繋がる良い機会となりました。

フィンランドが欧州委員会議長国として主催した会議でのプレゼンテーション。
Source: McKeown, Caroline [@cazmckeown]. Twitter, 9 Dec. 2019, https://twitter.com/cazmckeown/status/1203956094638407681

ドバイ万博で開催された国際会議でのパネルディスカッション。グローバル・コンピテンスの専門家と実務家と共に登壇。
Source: Qudwa (2022, February 19). Qudwa-PISA Global Competence Forum [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=9KHtnPcklvw&t=23972s
3. OECDで働くことの魅力
一番の魅力は、国際的なプロジェクトに携わることができ、一国内のプロジェクトでは見えにくい要因を国際比較することにより明らかにし、世界各国の暮らしをより良くするための政策提言をする機会があることです。PISA2018年度調査には79ヵ国・地域から60万人を超える生徒が参加しました。これだけ求心力のあるプロジェクトに関われることを光栄に感じつつ、参加者・協力者の努力に最大限応えるために、生徒たちの学びに関して有意義な政策提言をめざし日々模索しています。
研究と実践の懸け橋になれることもOECDで働くことの魅力だと思います。教育学、経済学、社会学、心理学、統計学といった様々の領域の専門家と議論する機会に恵まれる一方で、各国で教育に携わる人々と対話する機会にも恵まれています。それぞれの領域で蓄積された知識と最新の議論を生かして、どのように現存する問題を解決するか、もしくは来たる問題に備えるか、に取り組むことができるのは研究色の強い国際機関ならではの役目でしょう。
最後に、志を共にする優秀な同僚、参加各国の代表者、専門家、実務家と一緒に働けることは一番の喜びです。多様な社会・文化・言語背景の人々と、同じゴールを目指して協力することで、日々新しい発見と多くの学びがあります。
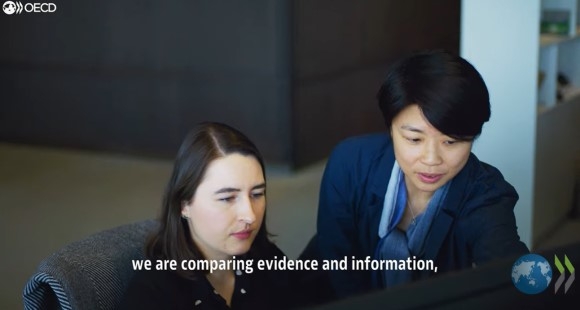
チームメンバーと共に。
Source: OECD. (2019, September 4). Creating better policies for better lives, together [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=6JstvTnZjHM
4. これからOECDで働きたい人へのメッセージ
OECDで働くことに興味のある方は、「力を合わせて創ろう、より良い暮らしのためのより良い政策」というOECDの大きな目標にどのように個人として貢献できるかを具体的に示す必要があります。そのためには、広い視野を持ちつつ、特定の専門分野での見識と経験を深める事が重要だと思います。OECDが扱う社会問題は様々な分野にまたがるので、関連する他の分野の動向を追うことも役に立ちます。広い視野と特定分野の知識・経験に加えて、多様な背景の人々と共に働くことのできるコミュニケーション能力や交渉・調整力、そして複雑かつ前例のない問題に対処する問題解決能力やレジリアンスも大切でしょう。
公募採用を目指すと同時に、インターン、コンサルタント、ヤング・プロフェッショナル・プログラム(YPP)、JPO派遣制度などを活用して、先ずはOECD関連の仕事に関わってみることをおすすめします。私自身、OECDで働き始める前に、世界銀行でインターンとコンサルタントとしてベトナム国内の学習到達度調査に携わり、その後JPO派遣制度によりユネスコで南部・東部アフリカ地域の学習到達度調査に携わりました。この間にPISAに携わる国際的な専門家と議論する機会が多々あり、その時の経験がOECD公募採用に繋がったと思います。
