熊谷裕司 OECD原子力機関(NEA)原子力安全専門官
2022年11月
1. 担当業務
2019年6月よりOECD原子力機関(NEA:Nuclear Energy Agency)において原子力安全専門官として勤務をしています。私は、これまで欧米諸国を中心に原子力の安全分野の研究や実務に携わってきたため、NEAではこの経験を生かして、世界各国の専門家たちと共に原子力安全分野の研究活動を推進しています。
私が担当している分野は主に、東京電力福島第一原子力発電所(1F)の事故に関連した国際共同プロジェクトと原子力リスク評価に関するワーキンググループ(WGRISK)です。前者は、1F事故を背景として、NEAにおいて様々な国際協力が進んでおり、シビアアクシデントといわれる過酷事故が発生した際の事故進展の解析や1Fの燃料デブリ取出しに向けた準備を行うプロジェクトが主な活動です。後者のWGRISKは、リスク情報規制や安全管理における確率論的安全評価活用に関する活動を行っています。私は、これらの活動の技術助言、立ち上げ、会議運営・進行等をプロジェクトメンバーやNEA加盟国の専門家と協力して行っています。
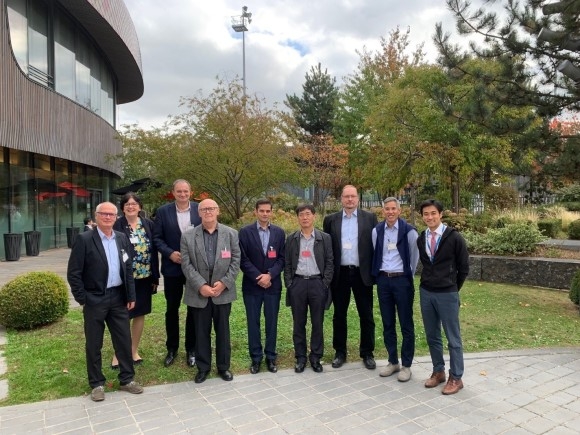
WGRISK Bureauメンバ-と
2. 特定の業務のエピソード
NEAの福島関連の活動は1F事故後の2012年より開始され継続してきましたが、後続のプロジェクトを2022年に立ち上げるにあたり、日本をはじめ世界各国の関係者と協議を続け、プロジェクトの枠組み構築から契約書の作成や締結に至るまで、新規プロジェクト立ち上げに幅広く携わりました。
特に難しい局面としては、プロジェクト立ち上げ準備の際に、ロシアによるウクライナに対する軍事侵攻が勃発し、元々のプロジェクトメンバーであるロシアと新規メンバーであるウクライナの調整を行う際には神経を使いました。
福島関連の活動は、世界初の試みが多く、未解決な技術分野の課題を扱うため、非常に複雑かつ難しい課題が山積みで、一企業、一国で解決するのは困難であるため、国際的な協力が必須の領域と言えます。従って、福島の課題に取り組むため、各国の専門家と協力し国際的な枠組みを構築し、2022年7月のFACE*プロジェクト立ち上げに貢献出来たのは、私の中で最も記憶に残っている活動です。
*FACE: Fukushima Daiichi Nuclear Power Station Accident Information Collection and Evaluation

FACEプロジェクトのキックオフ会議
3. OECDで働くことの魅力
OECDで働く事の魅力は挙げたらきりがないぐらいありますが、私の中で代表的なものは以下のとおりです。
- 私はキャリアのうちの10数年間を英米中心に過ごしてきましたが、世界各国からの専門家に囲まれて業務を行うのは今回が初めてで、OECDでの業務を始めた当初は、彼らの英語や仕事文化に慣れるのに苦労しました。一方で、この環境下で業務を行うことで、多国籍な職場環境においても通じるコミュニケーション能力、迅速な問題解決能力、ファシリテーション能力、リーダーシップ能力等を身に付けることが出来ました。
- OECDでは、欧米のジョブ型の雇用形態をとっており、上司の役割は、物理的な時間管理ではなく、部下の業務の仕組みづくりを行い裁量権を与えることです。実際マイクロマネジメントと結果は繋がらないことを皆が認識しています。このジョブ型の雇用形態が、職員のやりがいに繋っているのだと思います。
- 欧米ではアンチ前例主義の考え方が浸透しているため、コロナ後も旧に復すのではなくニューノーマルへの移行が素早く行われ、ネガティブな環境さえも、新しい変革のチャンスだと捉えている人が多かったのが印象的でした。
- 人材の流動性の観点からは、コア技術を持つ人材が各機関を渡り歩くことで多様性が向上するため、日本のような高すぎる帰属意識から生じる各機関の間にある高い垣根が取り除け、健全なコミュニケーションが図れることも学びました。
- ジェンダーの観点としては、前職までは男性中心の職場環境でしたが、NEAの上層部は女性が多数派で、私の部署も半数以上が女性職員という状況です。このような環境での職務を通して、例えばこれまで男性主導で行われてきた評価基準とは異なる基準が存在することに気づき、多くの新しい価値が創出されることを実感しました。
- 日本国内では気づかなかった自分の強みや弱みを再認識することができ、それにより自身の国際コミュニケーション等の強みを更に伸ばすことに注力できたこともOECDで働くことの大きな魅力であったと感じます。
以上のような能力や考え方を短期間で身に付けることが出来たのは、OECDでの経験のお陰だと思っています。更に、OECD経験者が、このような国際機関のポジティブなワーキングスタイルを日本にも伝え、変革していくことは非常に重要な役割だと思っています。
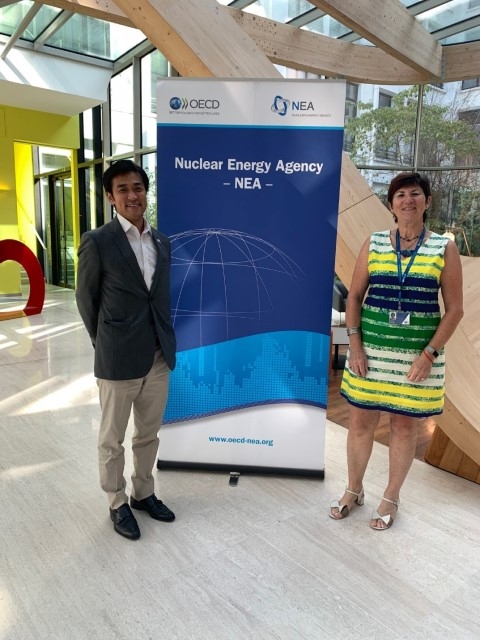
上司Veronique Rouyer原子力安全技術・規制課長と
4. これからOECDで働きたい方へのメッセージ
私は、当初OECDにはスタッフオンローンという日本企業からの派遣という形で職務をはじめ、その後正規職員として採用されました。やはり中に入ってみないと分からないことも多いため、少しでも国際機関に関心のある方は、行動力を発揮して、周りを説得して、インターン、JPO、スタッフオンローン等どういう形でもいいので、一度OECDにまずは足を踏み入れることをお勧めします。
また国際機関の職員は、当然先進国の優秀な人材が集まっておりますが、それ以上に選りすぐりの稀有性を持った人材の集まりだと思います。そのような稀有性を持った人たちに囲まれて業務を行っていくことは、今後のキャリアにおいて、これ以上ない貴重な経験になると思います。私は、息子にも、パパやママ、先生のいうことを必ずしも聞く必要はない、と普段から言い聞かせておりますが、人が言っているということは、誰かが既に実施しているということです。OECDに応募しようと思っている方は、常日頃より、出来るだけ人がやっていない道を進んで、ご自身の稀有性を高められ、人とは違う自分の価値を高めて挑戦してみてください。その結果として、OECDへの道、またその先の道が開けるのではないかと考えています。Control your own destiny or someone else will!(GE元CEOジャック・ウェルチ)。
最後になりましたが、パリでの生活は最高です。フランス語は、業務上必須ではありませんが、話せたら人脈が広がり生活が充実するというモチベーションで私は頑張って勉強しています。またスポーツ全般が趣味なのですが、特に最近はマラソンにハマっているので、セーヌ川、エッフェル塔、ルーブル美術館等パリの街を日々駆け抜けるのはこの上なく気持ちいいです。きっかけは何でも良いと思いますが、何をしたい、どこに住みたい、といった願望は重要だと思っています。OECDやパリが、ご自身のその願望を満たしてくれるとお考えであれば、是非挑戦してみてください!

学生時代から世界に出て良く学び良く遊び良く運動する
