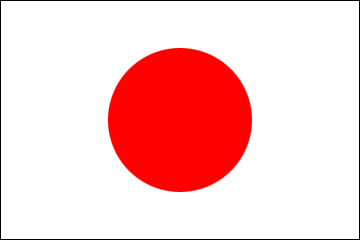OECDはホームセンタ-
2021年3月
OECD日本政府代表部大使
岡村 善文

社会において皆が円滑に生活するために、規則が必要です。たとえば交通規則がないと、たちまち交通は麻痺します。混雑する交差点には信号が必要ですね。世界経済も同様で、経済活動の自由といってもなんでも許されるわけではありません。貿易、投資、税制、企業行動などについて、皆が公平に経済活動を進められるように、また社会に弊害が出ないように、青信号・赤信号を決めなければなりません。
でも国際社会には立法機関はないし、取り締まりを行う警察もいない。どうやって規則をつくり、どうやって守らせるのか。ひとつのやり方は、多国間条約です。国が集まって交渉し、規則を条約・協定として締結すれば、それはお互いに守らなければならない約束、つまり国際法上の拘束力を持ちます。この最大の例のひとつが、「関税および貿易に関する一般協定」いわゆるGATTです。世界中の国が互いに貿易をする上での、関税その他について取り決めたものです。この協定から発展して設立された世界貿易機関(WTO)が、協定の違反を監視したり、国どうしの紛争を裁定したりしています。条約・協定には各国に守る義務があるので、このやり方で決めていけば実効性のある規則ができます。
でも、それだけに規則を決める交渉はたいへんです。長い月日がかかるのが通例です。また、守れない約束はできませんから、国内に事情を抱えた国は厳しい内容には首を縦に振りません。どうしても誰もが容認できる、最小限の内容にとどまってしまいがちになります。そして条約・協定が発効するためには、一定の数の締約国が批准という国内手続き(日本の場合は国会承認)を済ませないといけない。規則が多国間条約として成立するのは簡単ではないのです。
そこにOECDが登場します。OECDは、そんな厳密な条約・協定でなくても良い、と考えます。契約書みたいに縛られるものでなくても、努力目標を紙に書いて壁に貼るようなものなら、規則は作れる。でもそんな紙だけでは、守られないじゃないか。いやいや、各国がそれを個別に実施すればいいのです。つまりOECDで規則を作って、各国はそれを国内で法律や行政規則にしていく。これがガイドラインとか紳士協定と言われるものです。OECD各国の間で内容を協議し、勧告というかたちで取り決めています。
これらのガイドラインや紳士協定は、単に国々の間で守るべき規則を定めるだけではありません。各国政府に、さまざまな分野においてどういう政策で臨むべきかの、国際的な標準を示すことになります。これは各国政府にたいへん助けになります。ふむふむ、このあたりを国内でも立法化しておけば国際的に遜色ないのだ、国内外での問題発生を未然に防げるのだ、と分かるわけです。それに法的拘束力が前提になっていませんから、かえって幅広く柔軟な内容を決めていくことができます。どんどん進化していく現代社会・経済です。それに対応して規則を制定・改訂していかなければならないときには、とても効率的なやり方です。
たとえば、「多国籍企業行動指針」は1976年に策定され、投資委員会 の検討を経て、現在に至るまで何度も改訂されてきています。これは、多国籍企業に責任ある行動を自主的に取るように求めるガイドラインです。多国籍企業は、国の管轄権を越えて活動しますから、一国の産業政策、税制、消費者利益、労使問題、人権保護などの管理が及ばなくなる可能性があります。この指針に基づいてOECD加盟国の中で共通して取り組めば、多国籍企業に責任ある企業行動を求めることができるのです。
の検討を経て、現在に至るまで何度も改訂されてきています。これは、多国籍企業に責任ある行動を自主的に取るように求めるガイドラインです。多国籍企業は、国の管轄権を越えて活動しますから、一国の産業政策、税制、消費者利益、労使問題、人権保護などの管理が及ばなくなる可能性があります。この指針に基づいてOECD加盟国の中で共通して取り組めば、多国籍企業に責任ある企業行動を求めることができるのです。
また、輸出にかかわる信用供与については、1978年に「公的輸出信用アレンジメント」を取り決めています。各国の政府系金融機関が融資や保険などを野放図に行い、輸出を行う私企業を支援すると、質と価格に基づく公平・公正な競争が損なわれます。また、諸政策の観点から各国が協調して輸出支援策を見直していこうとする場合もある。そうした問題を解決するため、OECD加盟国の間で紳士協定を作ったものです。そして、新しい問題がどんどん出てきますから、貿易委員会 (輸出信用・信用保証部会)で検討を重ね、毎年のように改訂してきています。
(輸出信用・信用保証部会)で検討を重ね、毎年のように改訂してきています。
これらはほんの一例。こういうガイドライン・紳士協定がいくつくらいあるかと数えたら、245本もあります。OECDのHP に一覧が出ています。実にいろいろな分野に及んでおり、OECDの用語で「法的文書(legal instruments)」と呼んでいます。各国が自国の国内で適用していくための「道具(instrument)」だということでしょう。木工をするには鉋(かんな)や鋸(のこぎり)、修理をするならドライバーやペンチ、塗装をするならペンキや刷毛、目的によってさまざまな道具が必要です。OECDは各国にそうした道具を提供します。OECDは各国にとって、そこに行けば必要な道具が見つかる、いわばホームセンターのような機関だと言ってよいでしょう。
に一覧が出ています。実にいろいろな分野に及んでおり、OECDの用語で「法的文書(legal instruments)」と呼んでいます。各国が自国の国内で適用していくための「道具(instrument)」だということでしょう。木工をするには鉋(かんな)や鋸(のこぎり)、修理をするならドライバーやペンチ、塗装をするならペンキや刷毛、目的によってさまざまな道具が必要です。OECDは各国にそうした道具を提供します。OECDは各国にとって、そこに行けば必要な道具が見つかる、いわばホームセンターのような機関だと言ってよいでしょう。